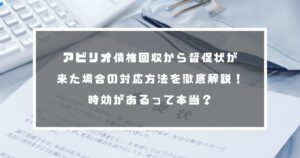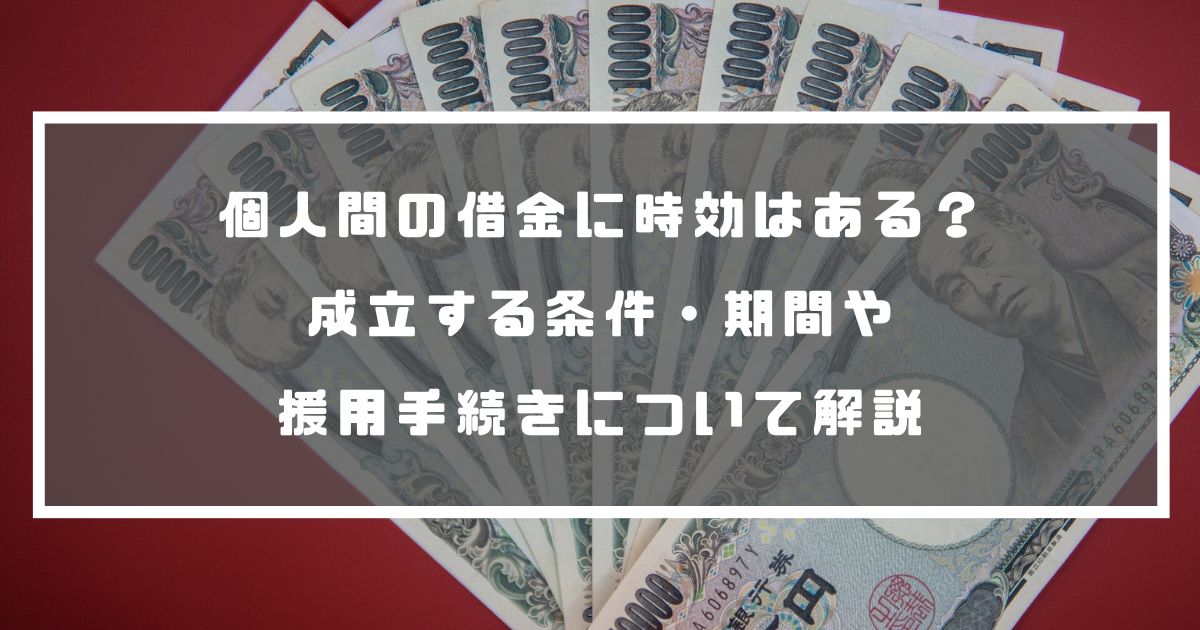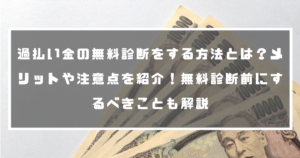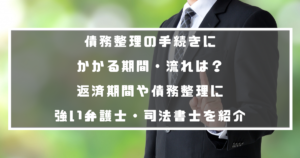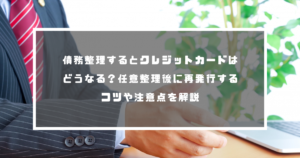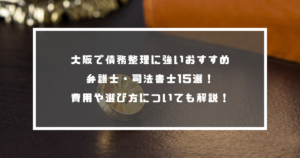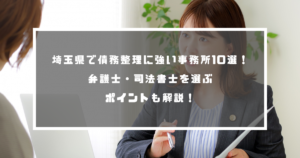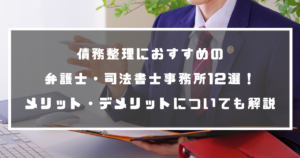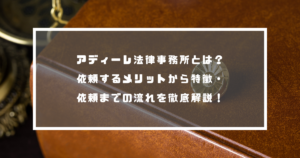借りたお金を返さないといけないと理解しているものの、返済が難しくいつ時効が成立するのか知りたい方もいるでしょう。
しかし、消費者金融や銀行など金融機関からの借り入れではなく、個人間の借金の場合時効が成立するのかどうかわからない方も多いのではないでしょうか。
結論からお伝えすると、個人間の借金にも時効は存在します。
しかし時効を成立させるためには、一定の条件を満たさなければなりません。
本記事では、個人間の借金の時効が成立する条件や期間、実際の手続きについて解説します。
個人間の借金に悩んでいる方は、本記事を読んで借金を時効にできるかどうか確かめてみましょう。
弁護士事務所・司法書士事務所
| ベリーベスト法律事務所 | なみき法務事務所 | はたの法務事務所 | ひばり法律事務所 | サンク総合法律事務所 | 東京ロータス法律事務所 | アース法律事務所 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
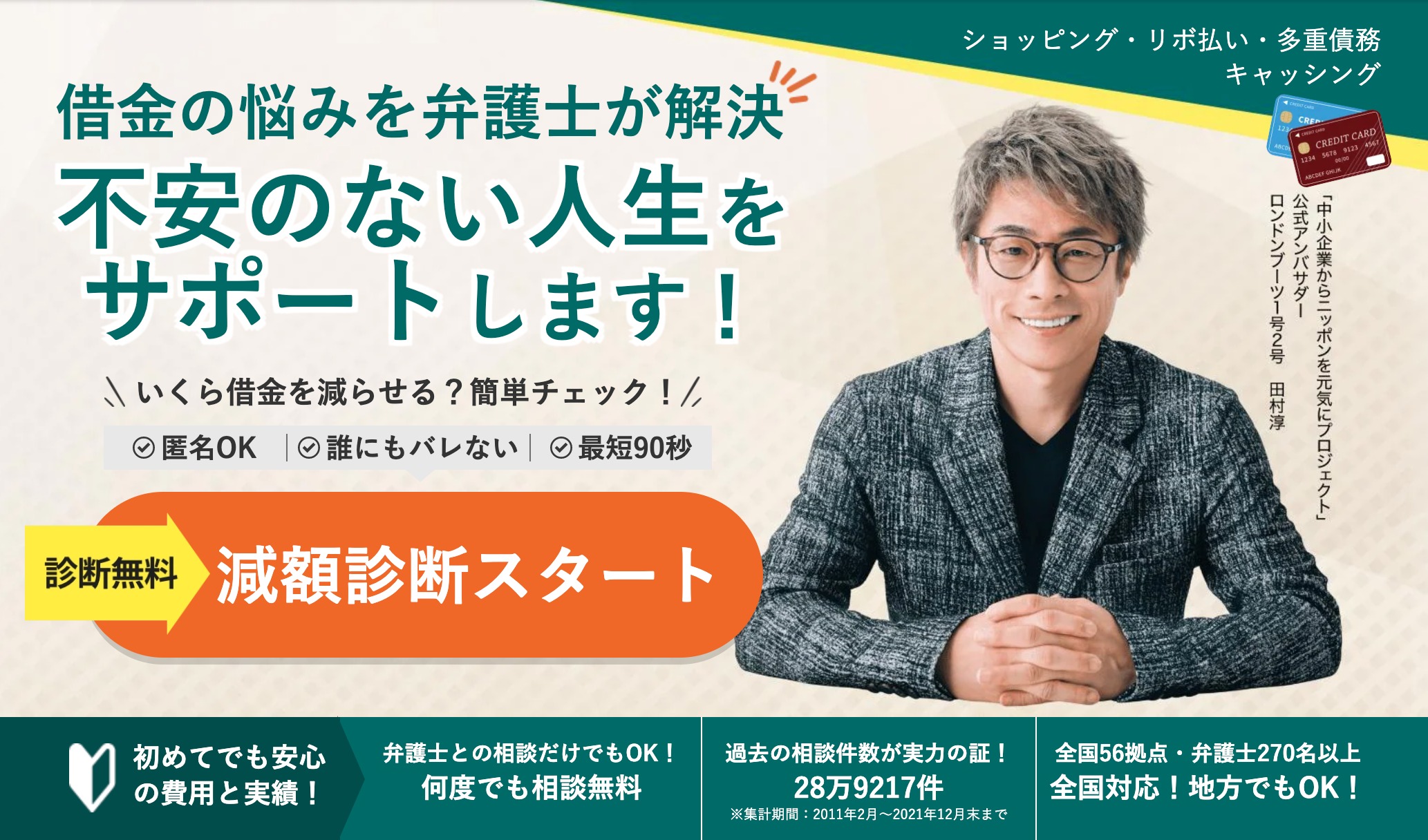 |  |  |  | 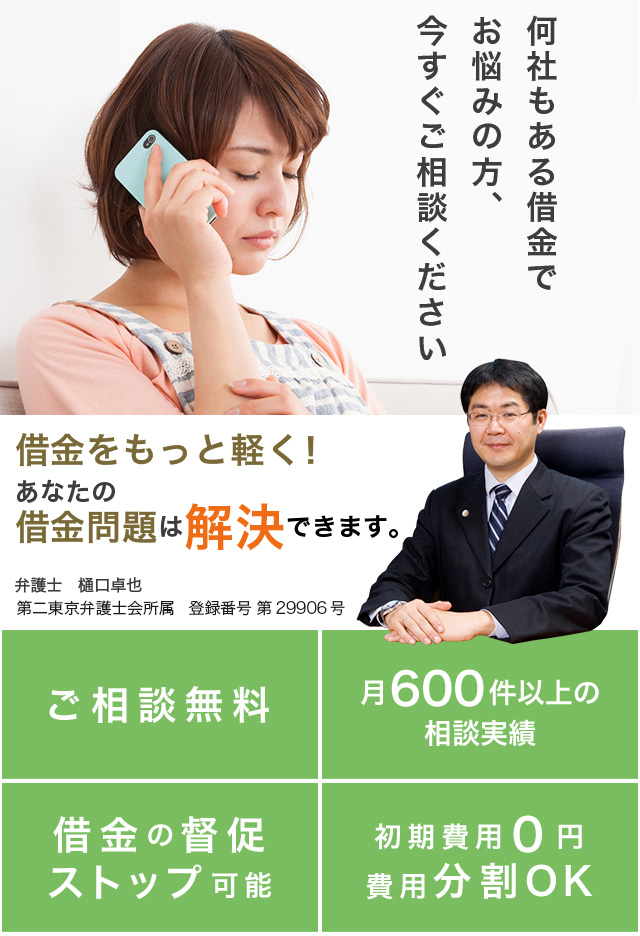 |  |  | |
| おすすめ ポイント | 何度でも相談無料 10年以上の豊富な実績 24時間365日相談受付 | LINEで気軽に相談 10年以上の実績 良心的な費用設定 | 全国出張費用が無料 司法書士歴27年 過払い報酬が安い | 女性専用の相談窓口 何度でも相談無料 秘密厳守だから安心 | 初期費用が完全無料 365日24時間受付 分割払いOK | 受任実績が豊富 休日も相談受付 何度でも相談無料 | 元裁判官がサポート Web相談は常時受付 借金問題は相談無料 |
| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 任意整理 | 1社22,000円〜 | 1社22,000円〜 | 1社22,000円〜 | 1社22,000円〜 | 1社55,000円〜 | 1社22,000円〜 | 1社22,000円〜 |
| 減額報酬 | 返還額の11% | 返還額の11% | 返還額の11% | 返還額の11% | 返還額の22% | 返還額の11% | 返還額の11% |
| 個人再生 | 495,000円〜 | 385,000円〜 | 385,000円〜 | 330,000円〜 | 要相談 | 330,000円〜 | 住宅なしの場合 330,000円〜※1 |
| 自己破産 | 385,000円〜 | 330,000円〜 | 330,000円〜 | 220,000円〜 | 要相談 | 220,000円〜 | 330,000円〜 |
| 過払い報酬 | 返還額の22%〜27.5% | 返還額の14%〜22% | 返還額の14%〜22% | 返還額の22%〜27.5% | 返還額の22%〜27.5% | 返還額の22%〜27.5% | |
| 対応地域 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |
| 詳細 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
個人間の借金に時効はある?

金融機関からの借り入れだけでなく、個人間の借金にも時効はあります。
法改正の影響で時効が成立するタイミングは、いつ借金をしたのかで異なります。
2020年3月31日以前に個人間で借金をした場合、時効は権利を行使できるときから10年間です。
2020年4月1日以降に個人間で借金をした場合、権利を行使できるときから10年間、あるいは権利を行使できると知ったときから5年間の早い方が時効として適用されます。
いつ借金をしたのかで時効成立のタイミングが変わるため、いつの間にか時効が成立していたケースもあるでしょう。
個人間の借金の時効の期間には、注意が必要です。
個人間で借金の消滅時効が成立する条件

個人間で借金の消滅時効が成立する条件は、次のとおりです。
- 時効の更新(中断)がない
- 返済期限から5年~10年経過している
- 消滅時効の援用手続きをしている
いずれか一つでも条件を満たしていないと、時効が成立しないため注意しましょう。
時効の更新(中断)がない
時効の更新がおこなわれると、個人間の借金の時効が成立しません。
条件を満たし時効の更新が適用されると、時効の期間がリセットされます。
時効の更新の条件は、次のとおりです。
- 裁判上の請求がおこなわれた場合
- 財産の差し押さえ・仮差し押さえ、仮処分があった場合
- 借金の返済意思を示す行為があった場合
たとえば支払督促の通知書が裁判所から送られた場合、時効の更新が適用され、時効の期間はリセットされます。
時効の更新がおこなわれると、時効が成立しません。
個人間の借金の消滅時効を成立させたい場合、時効の更新には注意が必要です。
返済期限から5年~10年経過している
個人間で借金の消滅時効を成立させるためには、返済期限から5年から10年経過している必要があります。
民法改正前の2020年3月31日以前に個人間で借金をしている場合、時効期間は10年です。
民法改正後の2020年4月1日以降に個人間で借金をしている場合は、時効が原則5年になりました。
しかし、個人間の借金で返済期日を設けていないときの時効は、お金の貸し借りがおこなわれた日から10年間です。
民法改正前と改正後で少し扱いが異なるため、個人間の借金の時効期間には注意が必要です。
消滅時効の援用手続きをしている
個人間の借金は、時効を迎えているだけでは消滅時効が成立しません。
借金の時効成立に加え、債務者が時効援用の手続きをおこなう必要があります。
しかし、時効の援用は専門的な知識が必要であったり、書類を用意しないといけなかったりと容易におこなえる手続きではありません。
消滅時効を成立させるために時効の援用の手続きをおこないたい方は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するとよいでしょう。
時効の援用とは?
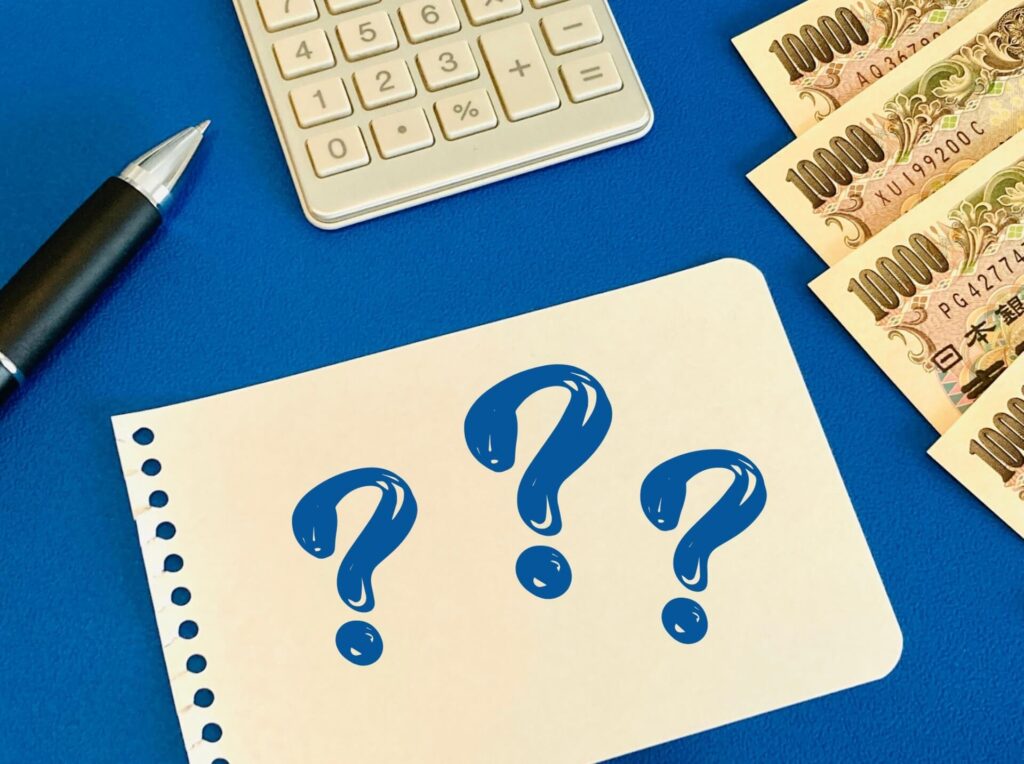
時効の援用は、時効が成立していることを債務者が債権者に主張する手続きです。
債務者へ債務の請求を一定期間しないと、借金は時効となります。
しかし、時効を迎えても借金の返済義務が自動的になくなるわけではなく、時効の援用をおこない債権者に借金の時効を主張しなければいけません。
借金の時効を成立させ、返済義務をなくすために必要な時効援用の手続きの流れをあらかじめ確認しておきましょう。
また、手続きにかかる費用の相場も解説するため、時効援用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。
時効援用の手続きの流れ
時効援用の手続きは通常1か月から3か月程度で完了します。
はじめに、消費者金融や銀行などの金融機関から発行されている通知書や、信用情報機関の記録から時効が成立するのかを調査します。
金融機関に直接情報開示を要求できますが、債務の承認とみなされ時効成立の妨げとなる可能性があるため注意が必要です。
時効の成立が確認できたら時効援用通知書を作成して債権者に送り、時効の成立を主張します。
時効援用通知書に記載する内容は、次のとおりです。
- 通知書を送る日付
- 債権の内容(債権者の会社名・住所・代表者名・借り入れ金額など)
- 時効が完成している事実
- 時効の援用を宣言
- 信用情報機関の登録情報の削除依頼
わからない場合は、弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。
消滅時効の成立を債権者が確認したら、消滅時効が成立します。
時効援用の手続きにかかる費用相場
時効援用の手続きにかかる費用は、大きく2種類にわけられます。
- 内容証明郵便の費用
- 弁護士や司法書士など専門家への依頼費用
内容証明郵便の費用は、最低1,300円程度です。
参考として、内訳を次の表にまとめました。
| 書類 | 料金 |
|---|---|
| 普通郵便料金 | 84円〜 |
| 内容証明郵便料金 | 440円〜 |
| 書留郵便料金 | 435円〜 |
| 配達証明料金 | 320円〜 |
また、弁護士や司法書士など専門家へ依頼するときの費用は、司法書士に依頼した場合、最低35,000円程度、弁護士に依頼した場合、最低30,000円程度が目安となります。
専門家への依頼費用は、事務所により異なるため注意が必要です。
内容証明郵便の費用と専門家への依頼費用をあわせても、30,000円程度から時効援用の手続きが可能です。
スムーズに手続きを進めたい方は、自身で手続きするのではなく弁護士や司法書士などの専門家へ依頼する方がよいでしょう。
個人間の借金の時効成立を主張する際に注意すべきこと

個人間の借金の時効成立を主張する際に注意すべきことは、次のとおりです。
- 借金の時効が成立する可能性は低い
- 借金の時効援用に失敗するリスクがある
知らなかったと後悔しないように、あらかじめ目を通しておきましょう。
借金の時効が成立する可能性は低い
個人間の借金の時効成立を主張する際は、借金の時効が成立する可能性が低いことを把握しておくとよいでしょう。
時効が成立するまでの期間は長く、債権者は時効の成立を阻止する方法を有しています。
たとえば裁判上の請求がおこなわれたり、財産の差し押さえがあったりした場合、時効の更新が適用され時効の期間がリセットされます。
また、債権者から口頭や書面などで催告があった場合は、時効の完成猶予が適用されて時効のカウントが一時停止し、6か月間は時効が成立しません。
債権者にも権利があり時効の成立を阻む方法がある以上、時間が経つのを待てば時効が成立すると簡単に考えている方は考えを改めた方がよいでしょう。
借金の時効援用に失敗するリスクがある
借金の時効援用に失敗すると、次のようなリスクがあります。
- 債務の承認とみなされ時効の更新が適用される
- 遅延損害金が返済金額に加算される
- 督促が再開される
時効援用の手続きは、ノーリスクでできるわけではありません。
借金の時効成立時期を誤認し、時効成立よりも前に債権者に時効援用通知書を送ると、債務を承認したとみなされる可能性があります。
債務を承認したとみなされると時効の更新が適用され、時効が成立しません。
また、時効援用の手続きをおこなうために時効を迎えるまで滞納を続けると、遅延損害金が高額になるケースがあります。
時効援用が認められれば問題ありませんが、仮に時効援用が成立しなかった場合、返済金額に加えて高額の遅延損害金も支払わなければいけません。
時効援用に失敗した場合、返済金額が大きくなる可能性があるうえ、督促も再開します。
時効援用通知書には債務者の連絡先も記載されているため、今までは債権者に連絡先を把握されていないことで督促から逃れていた方にもデメリットがあります。
時効援用の手続きは借金が帳消しになるため非常に魅力的ですが、リスクもあるため慎重に検討しましょう。
個人間の借金の時効が成立しないときはどうすべき?
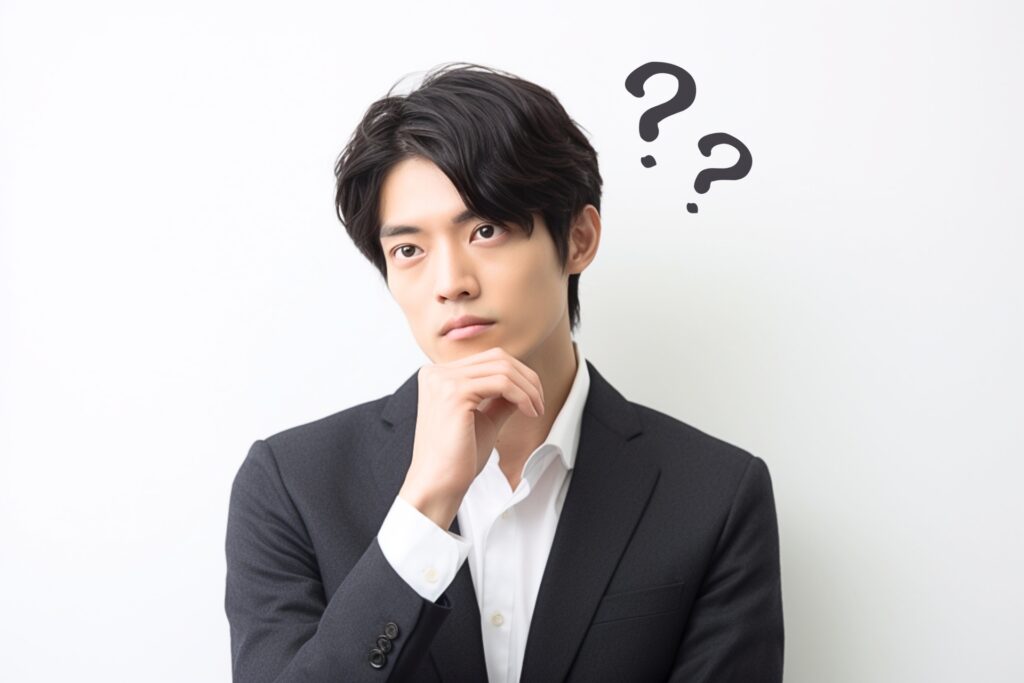
個人間の借金時効が成立しないときは、借金帳消しや減額ができる債務整理をおこなうとよいでしょう。
債務整理の手続きは、大きく3種類あります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
債務整理の利用を検討している方は、どの手続きが自身に適しているのか確認してみてください。
任意整理
任意整理は、将来の利息カットや支払いの分割を債権者と交渉し、借金の負担を軽減する方法です。
返済期間を3年から5年程度とし、債権者と和解します。
債権者からみて返済の見込みがあると判断できないと手続きを利用できませんが、任意整理を成立させるために年収に関する条件はありません。
任意整理の手続きをおこなうためには家計状況や勤務先などの情報を開示し、3年から5年程度継続して返済できる安定した収入があることを証明しなければいけません。
毎月の返済金額の目安は、毎月の手取り収入から家賃を差し引いた金額の3分の1です。
返済金額が目安の3分の1を超えている場合は、任意整理を成立させるのは難しいでしょう。
また、任意整理の手続きを検討している方は、借金の返済計画を明確に示す必要があります。
明確な返済計画を提示すれば債権者からの信用を得やすくなり、債務整理の手続きもスムーズに進むでしょう。
家族や周囲の方に知られたくない方は、裁判所を通さない手続きである任意整理の利用がおすすめです。
個人再生
個人再生は、債務を最大で元金の10分の1までカットし分割して返済する方法です。
任意整理とは異なり裁判所に申し立てをして手続きする方法で、返済期間は原則3年です。
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生の特徴は、法人が利用できないことです。
利用できるのは個人事業主を含む個人のみ、将来も継続して収入を得る見込みがあり、債務総額が5,000万円を超えていない場合に限ります。
給与所得者等再生は小規模個人再生とは異なり、債権者が反対しても個人再生が可能です。
小規模個人再生の条件を満たし、給与や定期的な収入の変動が小さければ利用できます。
給与や定期的な収入の変動幅が20%以内の場合、変動が小さいと認められることが多いです。
実務上は小規模個人再生の方が手続きが容易であるため、給与所得者等再生の手続きをする方は多くはありません。
自己破産
自己破産は裁判所への申し立てが必要なものの、債務全額を免除できる方法です。
同時廃止、管財事件、少額管財事件の3種類があります。
同時廃止は貯金や車などがないときにおこなわれる手続きで、破産管財人が選任されず手続きが終わるまでの期間が短く、費用が抑えられることが魅力です。
管財事件は高額な財産がある場合や申立人が大企業の経営者である場合に用いられる手続きで、破産管財人が借金の調査をおこない配当手続きを実施します。
同時廃止と比べると手続きが終わるまでの期間が長く、費用が高額になる点が特徴です。
少額管財事件は個人や自営業者の場合に用いられる手続きで、管財事件よりも手続きが容易で裁判所に納める予納金が少ないことが特徴です。
しかし、少額管財事件は法律で規定されている手続きではありません。
すべての裁判所で運用されているわけではないため、注意しましょう。
自己破産の手続きが完了すれば借金が免除されるため、任意整理や個人再生のように返済を続ける必要がありません。
借金の免除を希望する方は、自己破産を検討してみてください。
個人間の借金が返済されない場合の対処法

個人間の借金が返済されない場合の対処法は、次のとおりです。
- 支払督促・少額訴訟
- 通常訴訟
- 強制執行
それぞれの詳細を解説します。
支払督促・少額訴訟
個人間の借金が返済されない場合、お金を返してもらう方法に支払督促や少額訴訟があります。
支払督促は債権者が申し立てをおこなうと、簡易裁判所が債務者に対して金銭の返済を命じる法的な手続きです。
請求限度金額に上限がなく一括請求がおこなえるほか、裁判所にいく必要がなく書類審査のみであることが特徴です。
少額訴訟は原則1回のみで終了する裁判で、請求金額が60万円以下の場合のみ利用できます。
申し立て費用が安く、手続きにかかる期間が短い点が魅力です。
しかし、請求金額の上限が60万円までであるため、借金が高額である場合は支払督促を利用しましょう。
通常訴訟
通常訴訟は、支払督促や少額訴訟では解決が難しい場合におこなう法的手続きです。
少額訴訟よりも厳格な雰囲気でおこなわれることが多く、原告と被告が何度も証拠の提出をおこないながらやりとりするため解決までに時間がかかります。
しかし、借金が60万円を超えている場合や債務者の住所がわからない場合は少額訴訟を起こすことはできません。
貸している金額が60万円を超えている場合や、お金を借りている方の住所が不明である場合は通常訴訟をおこないましょう。
強制執行
強制執行は、借金が返済されない場合に裁判所や執行官などが財産を差し押さえて強制的に債権を回収する方法です。
強制執行をするためには、確定判決や仮執行宣言付損害賠償命令などの債務名義が必要になります。
債務名義は、強制執行により実現が予定される請求権の存在や範囲、債務者などを示した公の文書を指しています。
強制的に回収できるため非常に魅力的ですが、専門的な知識が必要であり自身でおこなうのは困難でしょう。
強制執行を検討している方は、弁護士や司法書士への相談がおすすめです。
借金の時効についてよくある質問

借金の時効についてよくある質問は、次のとおりです。
- 時効の援用は個人でおこなえる?
- 借金を放置して5年以上経過したら返済の義務はない?
借金の時効への理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
時効の援用は個人でおこなえる?
時効の援用は、個人でもおこなえます。
しかし、消滅時効を迎えているのか、時効が更新されていないのかの判断を自身でおこなうのは、専門的な知識が必要となるため困難でしょう。
また、債権者へ連絡をとったときにうまく言いくるめられて借金があることを認めてしまい、時効の援用ができなくなる可能性もあります。
手続きは個人でも可能ではありますが、リスクがあるため弁護士や司法書士などの専門家に任せた方がよいでしょう。
借金を放置して5年以上経過したら返済の義務はない?
借金を放置して5年以上経過していれば、返済の義務をなくせる可能性があります。
長期間放置しており請求がきていない場合でも、借金の返済は必要です。
しかし、借金の時効が成立している場合、時効援用の手続きをすれば借金の返済義務から解放されます。
ただ放置しているだけでは借金の返済義務はなくならないため、必ず時効援用の手続きをしましょう。
また、時効援用の手続きは専門的な知識も必要で、容易ではありません。
スムーズに手続きを進めたい方は、弁護士や司法書士などの専門家へ依頼しましょう。
まとめ
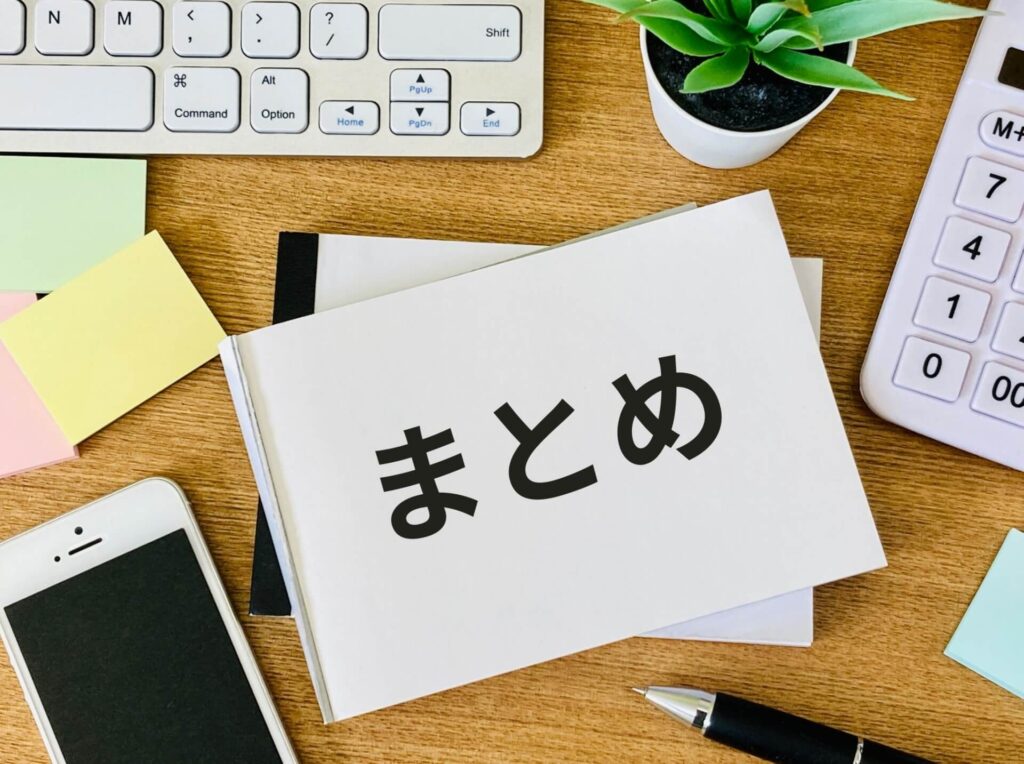
消費者金融や銀行などの金融機関からの借り入れではない、個人間の借金でも時効は存在します。
たとえば、時効の更新がなく返済期限から5年〜10年経過したうえで、時効援用の手続きをした場合、時効は成立します。
しかし、債権者にも時効の更新をする方法があり、時効援用の手続きを成立させることは容易ではありません。
時効援用の成立が難しい場合は、借金の帳消しや減額が可能な債務整理を利用するとよいでしょう。
ただし時効の援用も債務整理も専門的な知識が必要で、素人が簡単に手続きできるものではありません。
いずれかの方法で個人間の借金を解決したい方は、弁護士や司法書士などの専門家へ相談しましょう。